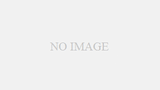満 18 歳まであと数か月、というところで今年の春に息を引き取った実家の柴犬。14, 5 歳くらいから少しずつ弱りはじめ、ここ数年は介護状態でした。
食欲はあるし、特に体の異常は見られなかったので予防接種を受けるのみで、動物病院には行かず、ずっと自宅で世話をしました。
最後に予防接種を打ちにいった際、家での様子を伝えると痴呆もあるね、と先生がおっしゃっていたそうです。
犬が老いていく様子も人間と同じで、どんどん小さな子供にかえっていくかのようでした。
足腰から少しずつ弱り始めて、痴呆も始まりました
まずは少しずつ足が弱り、お散歩のときに足がもつれるようになり、長い距離を歩きたがらなくなりました。
同時に、眠っている時間が増え、起きているときは人を恋しがり、暑さや寒さが苦手になりました。
そこで、昼間は外に出ていた生活から、一日中家で過ごす生活へと徐々に変えてゆき、エアコンや毛布、湯たんぽなどで暑さや寒さの温度調節をしました。
春や秋の気候の良い日中は日向ぼっこできる場所や、たまに外へ移動。家庭菜園で作業する父や、洗濯物を干す母が近くにいると嬉しそうでした。
実家では幸い、セミリタイア状態の両親と、比較的時間の融通が利く妹がいるので、おじいちゃんわんこを介護できる体制は整っていました。
痴呆が進むと、わんこは部屋中を徘徊するようになり、変な場所にすっぽりとはまってしまうことも。悲壮な鳴き声で異変に気付いて救出することもしばしばありました。
テーブルの脚などに頭をぶつけることもあるので、家具を移動して広いスペースを確保、そのうちさらに足腰が弱ると、徘徊時にパニックを起こしたり、倒れて動けなくこともあるので、今度は柵を使って動ける範囲を狭くしたりとわんこの様子や体調に合わせて試行錯誤を繰り返しました。
私は家人が不在のときに面倒を見ていました。足腰の強さを維持できるようにと、歩くことを嫌がらない範囲でなるべく外に出して庭を自由に歩かせていました。
犬の痴呆について調べた結果、のびのびと生活させてあげること、体の機能低下に対する恐れを取り除いてあげるのが良さそうだと感じました。
わが家の場合ですが、目や耳が衰えてくると、人の気配にとても敏感になりました。人がいないと、ずっと声を上げていることがあります。
とても大きな声で、元気なときとは違う声で鳴くので、最初は聞いているこちらがどうしてよいか分からず、胸を締め付けられるような思いをしていました。
とりあえず、そんなときは近くに行って大丈夫だよ、近くにいるよ、と声をかけて体をさすって落ち着かせようとしました。寝たきりも後半になってからは床ずれもできるようになったので、体勢を変えてあげたりすることも。
それで収まるときもあれば収まらないときもあり、何か体の痛みを訴えているのか、それともほかに何か言いたいことがあるのか…、鳴き声だけでは理解ができず、こういうときは辛くてたまりませんでした。介護は本当に試行錯誤の繰り返しです。

老犬を介護する中で最も大変だと感じたのは夜泣きです
私が一番きつく感じたのは夜泣き。わんこはだんだんと昼夜逆転の生活をするようになり、その生活に人間が合わせていくのが大変でした。
昼と夜の行動が逆だったらどんなに楽かと、そして、たまに泊まる程度の私でこれなのですから、一緒に暮らす家族はどんなに大変かと頭が下がりました。
昼間はほぼ眠っていて、夜は暗いのが不安なのか、遠吠えのような声で数時間おきに鳴き続けます。柴犬の鳴き声はなかなか大きいので、都会暮らしでは近所迷惑になるかもしれません。
でも、矛盾するかもしれませんが、大きな声で鳴いているうちはまだまだ元気がある証拠なのでほっとしていたのも事実です。本当に弱りだしたら、大きな声を出せなくなるので、それはそれで切ない気持ちになりました。
ひとつ、とても助かったのは排泄に関することです。ほとんど粗相をしませんでした。
というのも、わが家のわんこは足腰が弱っても、家の外で出したいという強い意志があり(笑)、トイレを催すたびに外へ連れていけと言わんばかりに、ワンワンと催促されたのです。
さすがに寝たきりになってからはトイレシートになりましたが、自力で排泄できる間は何時間かおきに交替で家人が外へ連れ出すという生活をしました。
食欲があるのは元気がある証拠
また、ずっと食欲は衰えませんでしたので、それがとても嬉しかったです。動物は食欲がなくなった時が危ないと聞いていましたが、本当だと思います。
亡くなる一週間くらい前まで、食欲はしっかりとありました。ただ、少しずつ量は食べられなくなりますし、視力も落ちていったので自分でうまく食べることができなくなります。
食事の際は、誰かがそばに付き添って体を支えたり、食べやすい体勢を取らせたりして介助していました。
ごはんは、手作りとカリカリの両方をあげていて、歯が弱ってきたら手作りの柔らかいごはんだけを与えるように。
しっかり食べているのに体は少しずつ痩せていく様子を見るのは切なかったですね。老人はだんだんと食べ物から栄養を取れなくなっていくと聞きましたが、犬も同じだなと思いました。
老犬の介護を終えて感じたこと
ひとつだけ、もっとしてあげられたかもしれないと思うのは、「触れてあげること」です。
わんこを亡くしてから知ったのですが、痴呆のわんちゃんには、たくさん触れてあげるのがとても良いそうです。
鳴き声で駆け付けたときなど、声をかけながら撫でてもいましたが、足りなかったかな、と思うことがあります。
とはいえ、私は最後の数年間はいつお別れを迎えてもよいよう、覚悟をしながら向き合ってきたので、後悔はありません。どちらかというと、やり切った気持ちのほうが強くあります。
実家の家族はとても献身的に介護をしており、特に妹は後半ずっとわんこのために生活しているような状態でした。
実際に息を引き取ったときはとてもつらかったですし、みんなでたくさん泣いたけれど、家族も気持ちに折り合いがついていると思います。
わんちゃんがどういう風に歳をとっていくのかはそれぞれでしょうし、世話や介護も何が正解なのかは最後まで分からないと思いますし、実際に私もいまだに分かりません。
でも、分からないなりにどうしたらずっと仲良く暮らせるかを模索することはできます。そして、真剣に向き合えば、誠実に応えてくれるのが動物たちだと思うのです。
後悔のないよう、ペットを第一に考えた世話をするのが飼い主の役目なのかな、と思っています。
ワンポイントアドバイス
人間と同じように、わんちゃんにも近所にかかりつけのお医者さんがいると、何かあったときにとても心強いと思います。わが家は幼少期から同じお医者さんにかかっていました。(ただし、診察結果に疑問を感じて別のお医者さんに診てもらった経験もあります。)
介護用品はペットシートを購入した程度で、クッションやマットは人間と同じものを使いました。柵などは父の DIY で作成。ホームセンターにはありとあらゆるものが揃っているので重宝しました。